た行
た
ち
つ
て
と
耐震改修
既存の不適格な建物に対し、部材・フレームの補強、制振ダンパーの付け加え、免震化などの処置を施し、耐震性能を向上させる処置をいう。
耐震壁
地震に耐えられる力を持たせた壁のこと。垂直・水平にかかる力に抵抗し、安定した変形能力を持つ。
耐震構造
大地震にも耐えられるように、基本的な強度を上げている構造。具体的な構造形式としては耐震壁などをバランス良く配置し、平面・立面形状に特定の弱い層を持たない構造。基準となる「建築基準法」で、現在の耐震構造の基礎が規定されたのは1981年。そのため、住宅の耐震性を判断する目安として、この1981年の建築基準法に則ったものかどうかが問題になる。現在の新築マンションでは、基本的な耐震構造は備えており、大地震でも建物自体が倒壊してしまう可能性は非常に低くなっている。
耐震診断
現在使用されている建物に対し、要求されている耐震基準と同等以上の耐震性を確保されているか、耐震改修の要否を判断するもの。
耐震補強
建物の耐震性を高めるために、基礎や柱、梁、床、壁などの補強を行なうこと。筋交いの追加や、柱や梁の接合部分を強化する金物設置、壁(耐力壁)の量を増やすなどの方法がある。
対面式キッチン(I型、L型、U型)
キッチンの前面がカウンターになっており、リビングやダイニングに対面する形で作業できる開放感的なキッチンタイル。作業中も家族と対話しながらできるのが人気。ほかに1列に並べたI型、ワークトップの形から名が付いたL型、U型などがある。
耐力壁
ベアリングウオールともいい、柱や梁を使わずに壁そのものが上部の重さなどに耐えられる力を持たせた壁。耐震壁(地震に耐える力を持った壁)や、間仕切りとは区別する。
太陽光発電システム
太陽電池パネルで家庭内で使用する電気をつくるシステム。太陽光を集めて電気をつくり、インバータ(変換器)で直流電流を交流電流に変換する。主に屋根に設置する。
太陽光発電買取制度
太陽電池を使って家庭で作られた電力のうち、自宅で使わないで余った電力を、10年間電力会社に売ることができる制度。
ダウンライト
照明器具のひとつ。光源を天井に埋め込み、直接下方を照らす照明方式。器具自体がほとんど見えず天井面がすっきりする。
高さ制限
建物を建てようとする地区や地域で決められている建物の高さの限度のこと。建築基準法の規定の一つ。
ダクト
建物内で空気調節や換気のために空気を通す管路・風道のこと。また、一般に流体の輸送、地下の送電線・電話線などの収容に用いられている。
竪子(たてご)
格子や障子戸で垂直に組まれる細木。
垂木(たるき)
棟から母屋・軒桁にかけ渡して屋根板や屋根下地板を支える木材のこと。
吹き寄せ垂木は、垂木を2~3本ずつを一組として並べる形式。
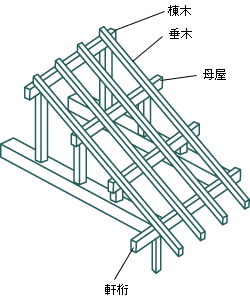
断熱材
空気の持つ断熱性能を活かして伝導熱量を少なくするもので、一般的にはグラスウール、ロックウールなどがある。一般に屋根や壁の下地と仕上げ材の間に使われる。
断熱ドア
ドアパネル内部に断熱材を充填し、ガラス部分に低放射複層ガラスなどを使用した断熱性に優れたドア。
地耐力
地盤が荷重に対して耐え得る強さのことで、地盤が1m3当たりどれくらいまで支えられるかを数値で示す指標。専門的には「長期許容応力度」という。地盤の上に建つ建物の種類(RC造、木造などの構造)や形状、地下水位、地質などによって変わってきます。建築基準法では、地耐力に応じた基礎構造で建築することが義務付けられている。
千鳥破風(ちどりはふ)
装飾や換気、採光のために設ける三角形の造形。
表中門(ちゅうもん)
主屋の正面にせり出す形の突出部分で、雪除け庇を持つ。豪雪地帯に多い。
長期優良住宅
耐久性や耐震性に優れ、世代を超えて住み続けられる住宅のこと。日本の住宅の平均寿命は30年と言われ、解体・建替えが繰り返されてきたが、住宅は「いいものを作って、きちんと手入れして、長く使う」べきとの考え方が広がりつつある。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は2009年6月に施行され、長期優良住宅の認定が始まった。一定以上の住宅性能や居住環境への配慮等、認定基準を満たした住宅には、期間限定で固定資産税や住宅取得税などの税制優遇措置も盛り込まれている。
調光器
調光器対応の照明器具を使用し、明るさの設定を記憶させ、簡単に複数の照明器具をコントロールできる機器のこと。明るさを調整できることで、同じ部屋で様々な雰囲気(シーン)を演出することができるほか、調光することで電気代の節約にもなる。

手斧(ちょうな)
大工道具の一種。木材を荒削りした後、平らにするのに用いる。
直接照明
全ての光が下方向に直接目的物を照らす照明方法。目的物への照明効率は高いが、天井が暗く強い影ができる。
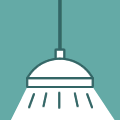
付書院(つけしょいん)
床の間わきの縁側沿いにある開口部のこと。原型は貴族や僧侶が読書などをするための机がわりに造られた縁側に張りだした出窓のようなもので、開口部に小障子を入れ、明かり取りとしていた。後年、床や床わき棚がセット化され、座敷飾りの定番として定着した。
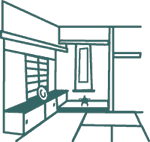
継手・仕口
金物などを使わず木同士で組み合わせる日本の伝統的な建築技法。継手は、材を延ばすために同じ材で継いでいくこと。仕口は、ある角度を持って接合することを言い、同じ材を直角や斜めに組む組手と、柱などに横の材を差し込むような差口がある。
坪単価
一坪(約3m2)あたりの建築費のこと。部分工事費をその部分の面積坪数で割った値。面積の単位をm2とするときは「平米(へいべい)単価」という。
TES(テス)
Thin and Economical Systemの略で、ガス温水冷暖房システムのこと。大型のガスボーラーを設置し、キッチンや浴室などの水まわりへ給湯するほか、各居室への冷暖房機に温水を送って暖房や除湿をする。
出隅(ですみ)
壁同士、壁と柱、板同士などの2つの面が外向きに出会うところの出っ張った角のこと。逆に内側に出会ってへこんだ角は入隅という。
デッキ
アウトドアリビングの場として、リビングやダイニングの前庭につくった外部スペース。天然木材のものはウッドデッキと呼ぶ。
出窓
建物の外周壁より外へ張り出した窓。四角形のほか三角形や弓形のボウウインド、台形のベイウインドなどもある。部屋を広く見せる効果がある。
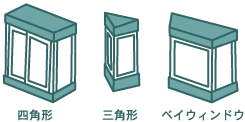
テラス
室内から庭に直接出入りできる広めのバルコニー。木の甲板を張れば、庭を眺めながら食事やお茶を楽しむことができ、屋内の延長スペースとしても利用できる。
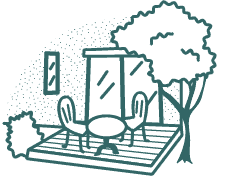
テレビドアホン
来訪者を室内のテレビ画面で確認できるインターホンの一種。録画機能付きのものもある。
展開図
室内の中央に立ったとき、四方に見える壁面の形状を立面図で描いたもの。平面図では分からない高さなどの確認ができる。開口部の位置やサイズ、コンセントやスイッチの位置、壁の仕上げなども描かれる。
天井
室内空間の上部を構成する面。普通は小屋組や床組などを隠すもので、張上げ天井・吊天井などがあり、特別の板などを張らずに屋根の野地裏や垂木をそのまま見せた化粧屋根裏もある。材質も様々で、防火、断熱、防音性に優れたものもある。最近では、天井高をより高く感じさせる効果のある折り上げ天井が、マンションなどに取り入れられるケースが増えている。
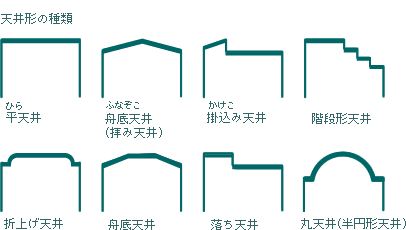
電動昇降装置
照明器具を電動で昇降させ、吹き抜けなどの天井の高い空間のランプ交換や、お掃除などのメンテナンスを容易にする装置。
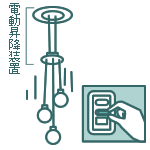
伝導熱
直接触れ合っている物体間を移動する熱。ホットカーペットやカイロなどは、そのものに直接触れることで暖かさを身体に伝える伝導熱を利用したもの。
天袋
和室の押入れ上部の戸棚のこと。押入れ上部以外の場所につくる場合は、天井からつり下げるつくりにする。 床の間上部の小ふすまの引き違い戸のついた棚のことも天袋と呼ぶ。天袋に対して、床の間の下に設けた物入れを地袋と呼ぶ。
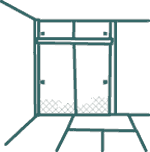
樋((とい))
屋根を流れる雨水を受けて地上または地下に流すために設けられた溝状・筒状の部材。材料は、塩化ビニール・金属薄板などが一般的だが木・竹なども用いられることがある。
雨水を軒先で受けるものを軒樋といい、その水を下に流すものを竪樋という。
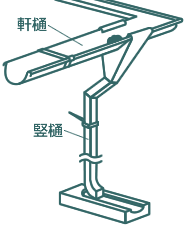
動線
住宅内、室内などの空間における人の動きを線で表したもの。空間で人の流れがスムーズに行えるように、設計段階で熟考することが大切。
胴縁(どうぶち)
柱や間柱などに、羽目板やボード類を取り付けるために用いる下地材のこと。水平に取付けることを横胴縁、垂直に取付けることを縦胴縁という。
通し柱
木造2階建ての建築物で、上階の軒から下階の土台までを1本で通した柱のこと。上階と下階を、途中中断した柱を通す管柱(くだばしら)より頑丈な構造になる。
独立行政法人 住宅金融支援機構
これまで国の住宅政策の中心的役割を担っていた住宅金融公庫が2007年4月に新たに組織、名称を変更し、「独立行政法人住宅金融支援機構」となった。主要事業は、「フラット35」など民間金融機関が行う長期固定金利の住宅ローンの支援。
床框(とこがまち)
床の間の前面に取り付ける横木。床板または、床の畳の端を隠す化粧框。
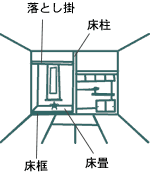
床の間
和室の一角に、座敷飾りとしてつくる場所。床は、床畳か床板を用い、床柱、床框(とこかまち)、落とし掛けなどで構成。床の間の壁面には書画を掛け、床には置物や花などを飾る。飾り物を引き立たせるために、凝りすぎないのが基本。そのうえで素材の組み合わせやバランスなどに気を配ることがポイント。床の間には真・行・草という分類があり、真は書院造り、行は数寄屋造り、草は茶室に用いられる。
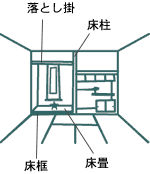
床柱
床の間の脇に立てる化粧柱。ヒノキや松などの柾目の通った面取りの角柱が正式だが、柱の四隅の面に皮を残している面皮柱(めんかわばしら)や円柱、紫檀・黒檀などの唐木、皮付きの自然木なども用いられることもある。
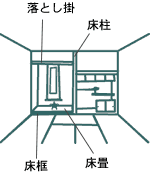
床脇(とこわき)
床の間や書院とともに床構えの構成要素の一つで、床の間の脇に違い棚や地袋、天袋などを設えた場所のこと。これらの形や組み合わせによる意匠の変化は無数にある。
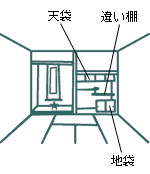
土台(どだい)
基礎の上に設置される、軸組の最下部の水平の木材のこと。柱からの荷重を基礎に伝え、柱の根元をつなぐ部材。基礎から出たアンカーボルトで固定する。最も地面に近い構造材のため、防腐性や防蟻性の高い材料(ヒバやヒノキなど)を選定したり、防腐処理や防蟻(ぼうぎ)処理したものを使用する。
トップライト
天窓または、天窓から採光すること。採光の効率がよく、適度の拡散光線が得られやすいため、室内で光のニュアンスを楽しむことができる。建築基準法の採光の規定では、天窓は壁に設けられた窓の3倍の有効面積を計上できる。住宅用開閉式のものは換気が目的。操作は手動と電動がある。
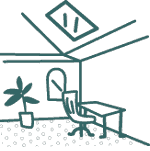
ドーマー
通室内の採光と外観のアクセントとして設けられる洋風住宅の屋根に突き出した三角屋根の窓のこと。
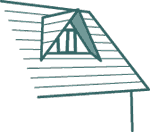
ドライエリア
地下室の採光・換気・防湿などのために、外壁に沿って設ける空堀のこと。奥行きは1m前後がいいとされ、地下室の湿気対策として効果的。
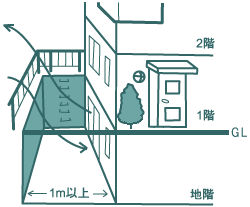
トラス
直線的な材料を用い、三角形を基本単位とする構造の骨組みで、各部材の節点を回転自由なピン接合としたもの。屋根組み・鉄橋などに使用。
トラップ
キッチンや洗面器、便器、浴室、洗濯機パンなどの排水管の途中に水をためる装置。下水道や排水管から臭気や虫などが室内に侵入するのを防ぐ。S型、P型、U型、ドラム型、わん型などの種類がある。
ドレン
雨水や雑排水、汚水などを流し出すための管や溝。
