さ行
さ
し
す
せ
そ
採光
室内に自然光を採り入れること。
建築基準法では建物の用途ごとに、床面積に対して必要な採光のための開口部の最小面積を定めている。
サイディング
乾式工法を採用した外装材のひとつ。耐久性・美観性・メンテナンス性に優れる。一般には、セメントや金属を使った外壁を指す。
竿縁(さおぶち)天井
竿縁と呼ばれる細い仕上げ材の上に天井板をのせて張る天井を竿縁天井という。竿縁が天井を支える役目も果たしている。竿縁の間隔には一般的な決まりがあるが、広い部屋なら広く、狭い部屋なら狭くする。また、竿縁の方向は、床の間と平行にする。
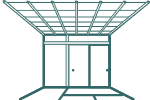
下がり天井
天井に梁やパイプスペースなどがあるため、天井から下に下がっている部分をいう。
図面上では点線で表示することが多い。
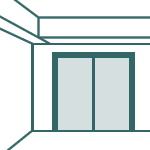
左官工
外壁に土やモルタル塗り、内壁の珪藻土仕上げ、タイルを取り付けるための下地づくりなどの作業をおこなう専門的な技術のある職人のこと。左官の技能を認定する国家資格として左官技能士がある。
左官工事
モルタル塗装や、コンクリート壁の補修、内装の漆喰・珪藻土塗りなど、壁や床を塗り仕上げをする工事の総称。コテなどを使って表面を塗り仕上げる。
サーキュレーター
室内の空気の質・温度を均一にする電気装置。直進性が高く、遠くまで届く風を起こし、冬場は上部に溜まりやすい暖かい空気を下方へ、夏場は下部に溜まる冷たい空気を循環させる。
差し鴨居
普通の鴨居と違い、梁のような太さをもつ鴨居。梁や胴差しなどのように構造材としての役割をもつ。
叉首(さす)
棟木を支えるための合掌形の斜材。
サービスヤード
台所に通じる屋外の家事作業スペース。洗濯機を置いたり、物干し場やゴミ置きのためのスペースとして使う。
サニタリー
住宅でのトイレや浴室、洗面室などの総称。これら3ヶ所が独立せず、1つのスペース内にある場合は「スリーインワン」と呼ばれることもある。
3路スイッチ
ひとつの照明器具を2ヶ所から点滅できるスイッチ。階段や廊下に取り付けることが多い。
仕上表
建物内部や外部の仕上げを表で示したもの。屋根や外壁、バルコニーの仕上げを示す外部仕上げ表と、各部屋の床、壁、天井の仕上げ、材料、品名、厚みなどの仕上げを示す内部仕上げ表がある。
敷居
門の内外を区切り、また部屋の区画を設けるために敷く横木で、建具を受ける横木を含む。引き戸の場合はその上にレールを設けるか、溝を彫る。鴨居と上下で対をなす。
式台(しきだい)
玄関の前に設けられた板敷きの部分。式台は色代すなわち送迎の挨拶をするところからきた。一般的に一階の床が高い住宅などで上がりやすいよう設けられている。
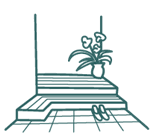
軸組
土台・柱・梁・桁・筋交いなどから構成されている壁体の骨組。略して「軸」ともいう。
仕口(しぐち)
2つ以上の部材がある角度をもって組み合わせて使用するとき、材どうしの接合部をいう。仕口は軸組全体の強度を大きく左右する。
システムキッチン
流し台や調理台、ガス台などを共通する基準寸法や仕上げなどでシステム化した台所設備のこと。広さや使い勝手に応じていろいろな組み合わせができる。一般には工場で部材、部品を生産し、ユーザーの要望やインテリア空間に組み合わせて部品などを選択し、現場で組み立てる。通常はベースキャビネットを並べた上に、一体となったワークトップをのせる方式のものをいう。最近では、電動で昇降する吊り戸棚や少しの力でも開閉できる引き出しなど、ユーザーに優しい工夫が施されている。スタイルとしてI型、L型、アイランド型、オープン型などがある。
自然換気
自然の温度差、気圧差を利用した換気を自然換気という。空気の移動は、温度差、気圧差のあるところに起きる。
温度差による換気での換気量は、開口面積のほか、給気口と排気口の高さの差や内外の温度差に影響を受ける。外気圧による換気での換気量は、窓など開口部の開放された面積のほか、内外の圧力差に影響を受け、換気量は、ほぼ開口部の開放面積と外気風速に比例する。
C値
相当隙間面積のこと。床面積1m2あたりの家の隙間の大きさを示す値。この数字が小さいほど気密性が高い住宅。単位はcm2/m2。
地鎮祭
建物を建築着工するために先立って、敷地の地主神を鎮め、工事の無事を祈願するために行われる儀式。
漆喰(しっくい)
消石灰に砂、すさ、布のりを混ぜ、水で練った左官材料で、壁面の仕上げ材として用いられることが多い。近年、自然素材として見直される傾向にある。
シックハウス症候群
化学物質過敏症のひとつで、新建材に含まれる接着剤や塗料から発生するホルムアルデヒドや、シロアリ駆除のための農薬などが原因となって、さまざまな体の不調が起こる。
湿式工法(しっしきこうほう)
モルタルや漆喰など水を混ぜた材料を使って、壁や床などをつくる方法。塗装、漆喰や珪藻土を使った左官仕上げ、コンクリート工事やタイル貼りなどもこの工法の一種である。天候に左右され、水が乾くまでの工期が必要となるため、乾式工法に比べて工期は長くなる。
地窓
床面に接した位置の窓。対角線方向の窓と組み合わせることで、自然換気に効果がある。
遮音材
遮音のために使用する材料。材質が緻密で単位体積当たりの重量が大きいほど遮音効果が大きい。コンクリート・石材・鉄板などが遮音材として使用される。
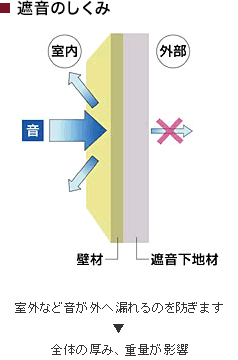
ジャロジー
建て具や窓に取り付けられた可動式の窓、またはガラリ戸。ジャロジーは、細長いガラスを羽目板状に並べた窓。
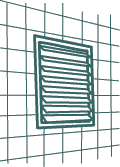
シャンデリア
複数の電球を用いた装飾的な多灯照明器具。チェーンなどで吊り下げるタイプと直付けタイプがあり、ゲストを招くリビングなどの主照明として使用されることが多い。昔は、ろうそくを枝形の灯器につけて点灯していたが、現在は電球とガラス部品を使用している。重量のあるものは、取り付け補強が必要。
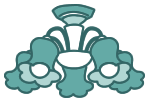
柔構造
建物がしなやかで柔らかい構造、骨組みにかかる力が小さく、超高層ビルに多く使用されている。
地震の時は揺れに抵抗せずにしなり、地面が揺れると、下の階から時間差で揺れ、地面が逆方向に揺れると、それに合わせてまた下の階から動いていく。これの繰り返しで地震が終わっても建物はしばらく揺れ地震のエネルギーを吸収する。ただし建物が柔らかくなると変形が大きくなるので、内外装などへの配慮が必要。
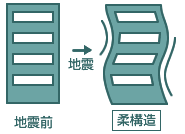
集成材
木材の板を繊維方向に組合わせ、接着剤で張り重ねて一つの材にしたもの。生きものである木は乾燥が不充分だと強度低下、反り、割れを生じるが、集成材に用いる木材は天然乾燥に加え、乾燥装置によって木の細胞膜中の水分まで放出させ、反り、割れを防ぎ、強度アップを図っている。
木材の欠点である節や割れがないため、品質を均一化でき強度性能が高く、複雑な形状の部材の成型も可能。
住宅性能表示
住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)」に基づいて、戸建住宅やマンションの性能を評価(表示)する制度。住宅の性能評価(表示)を第三者機関が、耐震性や省エネ性、防犯性などの10項目の評価を行い、住宅の質を高めることを目的にしている。
住宅・建築物省CO2推進モデル事業
国土交通省が、住宅・建築物における省CO2対策を推進するため、省CO2の実現性に優れた住宅・建築プロジェクトを公募し、整備費等の一部を補助する事業のこと。
収納
衣類や寝具、書籍、食器類などの生活用品をしまいおさめること。壁、床下、天袋など様々なものがある。最近では衣類を主に収納するウォークインクローゼットやキッチンに隣接した食品庫を設けたり、クローゼット扉と組み合わせて壁の中に設置する収納スペースも人気が高い。飾り棚でディスプレイのように楽しむ「見せる収納」もある。
樹脂製サッシ
フレームがプラスチック(硬質塩ビ樹脂)製のサッシ。アルミフレームに比べ熱を伝えにくい。
仕様書
工事内容のうち図面では表すことができない事項を文書や数値で表示したもの。
品質・成分・性能・精度、製造や施工の方法、部品や材料のメーカー、施工業者などを指定するもの。
上棟式
建築儀礼のひとつ。棟木を上げるときに行われ、大地をつかさどる神に感謝し、家屋の棟をつかさどる神々に工事の無事を祈願する。「棟上げ」「上棟祭」「建前」ともいう。
照明
住宅照明では、直接照明と間接照明がある。直接照明は天井灯やペンダント、スタンドなど光源からの直接光による照明方法。間接照明は光を壁や天井に当て、その反射光を利用する照明方法。目に優しく穏やかな光が得られるため雰囲気のある空間づくりに効果的とされる。
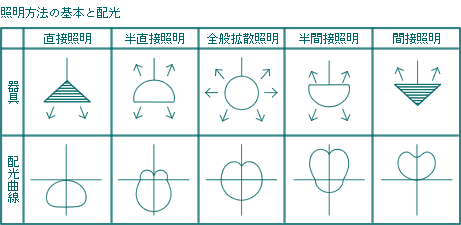
照度
光を受ける「面の明るさ」のこと。照度は単位面積あたりにどれだけの光が到達しているかを表し、ランプの明るさとは異なる。照度を表す記号はE、単位はlx(ルクス)が用いられる。場所ごとに、JISで規格が設定されている。
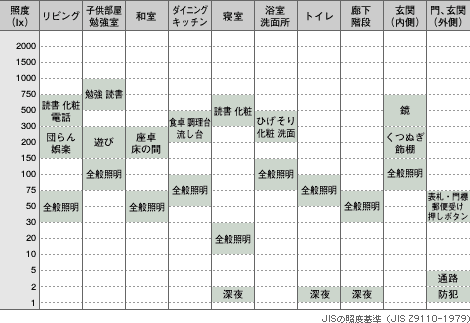
※20歳を基準にしています。高齢者は約2倍の明るさが必要です。
シーリングライト
天井に直接取り付ける照明器具の総称。
真壁(大壁)
日本の伝統的な壁のつくり。柱を露出させ、柱と柱の間に化粧仕上げした壁を納める工法。構造材が空気に触れ温湿度が調整しやすいので耐久性に優れる。これに対して柱が外部に現れないように仕上げた壁を大壁という。
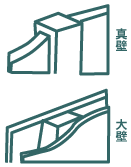
人感センサー
赤外線で感知範囲に人の体温程度の温度を感知すると自動運転する装置。主に玄関ポーチなどの照明、廊下やトイレなどに採用される。防犯用のアラームにも使用できる。
人造大理石
天然大理石に似せた模造大理石。合成樹脂と無機微粒子によってつくる。安価で各種の天然大理石の外観・色合いが得られ、品質も安定、軽量で取り扱いも簡単などの特長がある。キッチンのワークトップや浴槽などに使われる。
神代杉(じんだいすぎ)
杉の木が火山活動等で数百年間、水中や地中に埋もれ、炭化し変色したもの。渋い灰色が珍重され、工芸品、高級建築材として使われる。
スキップフロア
1つの空間の中で床の高さを変化させ、中2階のような部屋を作ること。各部屋の独立性を持たせることができる。
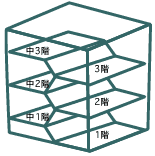
数寄屋造り(すきやづくり)
安土桃山時代から江戸時代にかけて完成された茶室建築の意匠を取り入れた建築様式。代表的なものに桂離宮があり、現代ではその様式は高級料亭や高級住宅に取り入れられている
筋交い
建物の軸組みに斜めに補強材を入れ、地震や台風など横からの外力に対する建物の耐力を高める柱構造をいう。一般的に、木造では柱の2つ割りなどを、鉄骨造りでは引張材として丸鋼などを用いる。
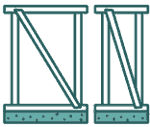
スーパーシェル工法
在来木造軸組工法のように軸(柱)ではなく、壁自体で強度を持たせるパネル工法。気密・断熱・耐震性を重視され、年間を通じて室内の温度変化が少ない。24時間連続換気が標準装備となるため、空気もきれいに保たれる。
スパン
梁を支える柱中心と柱中心の距離のこと。マンションでは、バルコニーや大きな窓がある開口部の一辺をスパンということが多い。間口や梁間とも。
スプリンクラー
散水装置のこと。
(1)庭園の芝生や畑などに設置し、回転して水まきをさせる装置。
(2)火災が発生したときに自動的に散水し消火する装置。消防法によって、一定以上の大きさのマンションやビルには設備が義務づけられているが、一般の住宅には設備の義務はない。
スポットライト
反射鏡やレンズを使用して集光性を高めた照明器具。部分的に明るく照らし、対象物を効果的に浮かび上がらせることかできる。調度品や絵画などにピンポイントで使用することが多い。
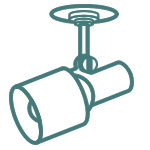
スマートハウス
IT(情報技術)を使って、住まいのエネルギーを総合的にコントロールする住まい。日本語に訳すと「かしこい家」。具体的には、HEMS(ホームエネルギー マネジメント システム)を中心として、太陽光発電システムなどで電気をつくる、蓄電池などで電気をためるシステムと家電や設備機器をつなげ、家全体のエネルギーをコントロール、最適にエネルギーを使うことができる家のこと。
墨出し(すみだし)
部材の取り付け位置や仕上げ作業のために、コンクリートや建材上に印をつけること。墨打ちともいう。柱や壁の中心線を示す墨を心墨、障害物によって直接墨出しができない場合などに、一定の距離を置いたところに引く墨を逃げ墨という。
スラブ
鉄筋コンクリート造の面構造のうち、水平面に使うものをいう。一般には鉄筋コンクリートの床板をいい、床として用いられるとき「床スラブ」という。
スレート
内外装の材料に使われる粘板岩。屋根葺きの材料として使われることが多い。天然と人工のものがある。天然スレートは粘板岩などを薄板に加工したもので、独特の質感があるが高価。人工のスレートはセメントに石綿などを混ぜて成型する。不燃性、耐水性、耐久性、遮音断熱性、耐候性に優れている。
スロープ
段差が生じる部分につくる傾斜した通路のこと。車いすでの通行には欠かせないもので、バリアフリー住宅でよく採用されている。
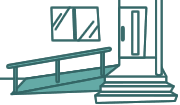
制振構造
建物に取り付けた機械的な装置や機構により、強風の時や地震の時に建物の揺れを小さく抑えることができる構造。エネルギー吸収機構構造などと呼ばれることもある。
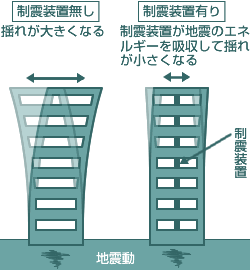
石膏ボード
石膏を主体に軽量の骨材を混ぜたものを心材とし、その両面をボード用原紙で覆って板状にしたもの。防火性、遮音性、寸法安定性に優れ、主に壁や天井の内装材、下地材、仕上げ材として使用される。
背割り
ヒノキやスギなどの木材は、丸太や柱の芯持ち材をそのまま乾燥させると「ひび割れ」が生じる。
丸太や柱は表面から乾き始めるので、乾いた表層だけ縮もうとする。しかし芯に近い部分にはまだ水分が残っているので、表層の縮みを邪魔する。そこで表面が引っ張り合い、割れ目が入り、ひび割れの原因となる。このひび割れを防ぐため、乾燥する前の丸太や柱にあらかじめ鋸目(のこめ=鋸を引いてできる切れ目)をいれ乾燥させるのが「背割り」という技法。こうすると、乾燥による縮みは鋸目のところに集中して、ほかの部分のひび割れがおきない。
この技法は日本で古くからおこなわれ、400年前の桂離宮の御幸御殿ではすべての柱に背割りが施されている。現在も背割り材は柱や床柱などに多く用いられている。
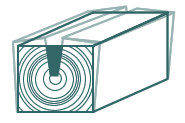
セントラルヒーティング
建物内部の一カ所に暖房用熱源装置を設け、各部屋に温風、温水、蒸気などを送り、暖房する中央暖房方式のこと。
全般拡散照明
半透過のカバーなどで透した光を全方向に広げた照明方法。
強い影や、眩しさが少なくできる。
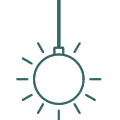
ゼロ・エネルギー住宅
建物を高気密・高断熱化し、高効率設備を利用することにより住宅で使われるエネルギーの効率を高める。さらに太陽光発電システムなどでエネルギーをつくることで、家庭で使われるエネルギー使用量を実質ゼロになるように対策をした住宅のこと。
増築
既存の建物全体を取り壊すのではなく、その一部を改造して床面積を増やすこと。敷地の中で別棟として建てられることも増築となる。建増しともいう。
袖壁
建物から外部へ突き出している壁。一般にその幅はそれほど大きくなく、機能としては構造上の目的を持つほか、目隠し・防火・防音や集合住宅のバルコニーに設けられる各戸の分離など、場所によっていろいろある。
外断熱(外張断熱)
鉄筋コンクリート造などの建物全体を外側から包むように断熱する方法。外側から断熱材で囲むので、内断熱より柱と断熱材の間の隙間はできにくくなる。熱損失が少なく、外気温に左右されないので、結露の心配が少ない。断熱面積が大きくなるので、多少コスト高になる。木造住宅の外断熱は「外張断熱」という。
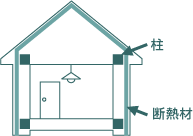
ソーラーシステム
太陽の光や熱を電気に変換して利用するシステムのこと。熱利用には、太陽熱温水器を用いて風呂の給湯に使う。集熱効率の高い集熱器と貯湯漕、ボイラー、冷凍機などと組み合わせると給湯、暖房、冷房にも利用できる。電気利用には、太陽のエネルギーを用い、太陽電池で電気に変換して利用する。
